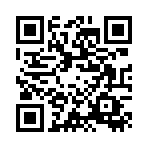2019年02月26日
3月定例会
今日も青空の好い天気でした。
今年は春の訪れが少し早いような気がします。
嬉しいですね。
さて、明日27日からいよいよ3月議会が始まります。
今議会には、平成31年度当初予算関係議案9件のほか、
専決処分の承認1件、補正予算3件、条例案件59件、
事件案件13件、人事案件3件が議案として提出されています。
しっかりと審議していきたいと思います。

今年は春の訪れが少し早いような気がします。
嬉しいですね。
さて、明日27日からいよいよ3月議会が始まります。
今議会には、平成31年度当初予算関係議案9件のほか、
専決処分の承認1件、補正予算3件、条例案件59件、
事件案件13件、人事案件3件が議案として提出されています。
しっかりと審議していきたいと思います。

Posted by 五十嵐かずひこ at
17:49
│Comments(0)
2019年02月15日
平成の経済史
平成の時代がもうすぐ終わろうとしている。
バブル経済で始まった平成の時代。
そしてバブル崩壊後デフレに突入した失われた20年。
やっと少し出口が見えてきたアベノミクス。
この時代を、大蔵官僚として20年、
その後、学者として10年、平成の世を過ごしてきた高橋洋一教授の著書、
「平成経済史」を読み解きながら紹介していきたいと思う。

【固定相場制への誤解が生んだ「プラザ合意」のデタラメ解釈】
昭和60(1985)年、ニューヨークのプラザ・ホテルで行われたG5において、
いき過ぎたドル高を是正する「プラザ合意」が発表された。
一般的にはドル高是正のために各国が外為市場に協調介入することになったとされているが、
真相は違う。
実は為替に介入するある状況をカッコつけて言い換えただけなのだ。
プラザ合意以降、「アメリカの圧力によって、政府が円高誘導をするようになた」といわれているが、
これはまったくのウソ。
むしろ「政府が為替に介入しなくなったことで円高になった」というのが正しい。
単に「介入をやめます」と宣言しただけのことを、
「プラザ合意」とカッコつけて言い換えているのが実情なのだ。
戦後長らく続いた1ドル=360円という円ドル相場。
なぜこれが続いたかについて、多くの人が
「固定制だからレートが変わらなかった」と思っているだろう。
だが、それは戦後日本経済における
”大いなる誤解”なのだ。
実は為替が絶対に動かないように、
政府は裏でガンガン介入してレートを維持していた。
つまり固定相場制というのは、
政府が為替に介入しまくることで初めて維持できるものなのである。
このことを前提にして、固定相場制から変動相場制に移行したとされる昭和48年以降を考えてみよう。
このときも、「変動相場制になりました。あとは市場に任せます」
というのは建前であって、実際には「ダーティ・フロート」と呼ばれる為替介入がずっと続けられていた。
ありていに言えば、円を安く設定しておくために、
裏では猛烈にカネを擦りまくっていた訳である。
ところがプラザ合意以降は、そうした介入をすることはなくなった。
為替レートを市場に任せ、本当の意味での変動相場制にしたのだ。
介入がなくなると、為替の動きはきわめてシンプルになる。
金融緩和で円の量を増やせば、円の価値がドルに対して相対的に低くなるから円安になる。
逆に、各国が金融緩和を進めているのに円の量を増やさなければ、円の価値が上がって円高に振れる。
実際に、プラザ合意前の円ドルレートは1ドル=235円前後だったが、
1年後には150円前後になった。
ところが円高不況の心配もなんおその。
プラザ合意からときを経ずして、
日本は「バブル景気」に突入していく。
※高橋洋一著「平成経済史」より転載。
バブル経済で始まった平成の時代。
そしてバブル崩壊後デフレに突入した失われた20年。
やっと少し出口が見えてきたアベノミクス。
この時代を、大蔵官僚として20年、
その後、学者として10年、平成の世を過ごしてきた高橋洋一教授の著書、
「平成経済史」を読み解きながら紹介していきたいと思う。

【固定相場制への誤解が生んだ「プラザ合意」のデタラメ解釈】
昭和60(1985)年、ニューヨークのプラザ・ホテルで行われたG5において、
いき過ぎたドル高を是正する「プラザ合意」が発表された。
一般的にはドル高是正のために各国が外為市場に協調介入することになったとされているが、
真相は違う。
実は為替に介入するある状況をカッコつけて言い換えただけなのだ。
プラザ合意以降、「アメリカの圧力によって、政府が円高誘導をするようになた」といわれているが、
これはまったくのウソ。
むしろ「政府が為替に介入しなくなったことで円高になった」というのが正しい。
単に「介入をやめます」と宣言しただけのことを、
「プラザ合意」とカッコつけて言い換えているのが実情なのだ。
戦後長らく続いた1ドル=360円という円ドル相場。
なぜこれが続いたかについて、多くの人が
「固定制だからレートが変わらなかった」と思っているだろう。
だが、それは戦後日本経済における
”大いなる誤解”なのだ。
実は為替が絶対に動かないように、
政府は裏でガンガン介入してレートを維持していた。
つまり固定相場制というのは、
政府が為替に介入しまくることで初めて維持できるものなのである。
このことを前提にして、固定相場制から変動相場制に移行したとされる昭和48年以降を考えてみよう。
このときも、「変動相場制になりました。あとは市場に任せます」
というのは建前であって、実際には「ダーティ・フロート」と呼ばれる為替介入がずっと続けられていた。
ありていに言えば、円を安く設定しておくために、
裏では猛烈にカネを擦りまくっていた訳である。
ところがプラザ合意以降は、そうした介入をすることはなくなった。
為替レートを市場に任せ、本当の意味での変動相場制にしたのだ。
介入がなくなると、為替の動きはきわめてシンプルになる。
金融緩和で円の量を増やせば、円の価値がドルに対して相対的に低くなるから円安になる。
逆に、各国が金融緩和を進めているのに円の量を増やさなければ、円の価値が上がって円高に振れる。
実際に、プラザ合意前の円ドルレートは1ドル=235円前後だったが、
1年後には150円前後になった。
ところが円高不況の心配もなんおその。
プラザ合意からときを経ずして、
日本は「バブル景気」に突入していく。
※高橋洋一著「平成経済史」より転載。
Posted by 五十嵐かずひこ at
22:01
│Comments(0)
2019年02月14日
混沌としてきた政局の見通し
平成の時代が残すところ2ヶ月半になった。
4月1日に発表される新元号が気になるところだ。
その4月には統一地方選が控えている。
鶴岡市では県議選候補者が一人増の少数激戦になりそうだ。
5月から新しい時代がスタートし、なんと今年のGWは
10連休だという。
そして6月にはG20が日本で開催され、
7月には参議院選挙がある。
場合によっては衆参ダブル選挙になる可能性も少なくない。
国会では予算審議の最中であるが、
野党は相変わらずのスタンスで揚げ足取りに躍起になっている。

【消費税増税について】
安倍首相は方針演説の中で、不退転の決意で実行すると言っている。
しかし、それは官僚が準備した原稿をそのまま読み上げただけで、
以前からリーマンショック級の事態が生じたら見直すとも言っている。
予算が通るまでは間違っても見直すとは言えないだろう。
言った時点で予算審議がストップし、内閣の総辞職になってしまう。
だが、予算成立後はわからない。
3月29日が期限のイギリスのEU離脱が混迷して、
こんな異常な事態が起こりうるのかというくらいに混沌としている。
このまま行ってしまったら、世界経済にとっては、リーマンショック級の大きな打撃となることは間違いない。
もうひとつ、中国の経済状況もかなり悪化している。
これも大きな危険を孕んでいる。
リーマンショック級の事件が2つも迫っているのだ。
しかも中国では消費税を16%から10%に引き下げる予定だという。
中国で下げると言っているときに、日本で増税するのは如何なものか。
こういった状況をみれば、消費増税を見送るのではないかと憶測できる。
【北方領土について】
もうひとつニュースで大きく取り上げているのが北方領土問題だ。
日本ではこの問題に関して、正確な歴史教育をしてこなかった。
政府にも大きな責任があると言える。
そもそも四島一括返還はあり得ない。
終戦の日付が日本と世界常識では違っている。
日本では8月15日を終戦記念日としているが、
世界の歴史では9月2日と認識されている。
終戦の後に違法に占拠されたという認識に無理がある。
日ソ共同宣言の後の経緯についても正しく伝えられていない。
1956年の日ソ首脳会談で、まず国交回復を先行させ、
平和条約締結後にソ連が歯舞群島と色丹島を日本に譲渡するという前提で、
改めて平和条約の交渉を実施するという合意がなされた。
ところが日本とソ連が仲良くなることを恐れたアメリカから待ったがかかった。
2島のみの返還は認めない。
4島一括返還でなければ沖縄の返還はあり得ないと恫喝された。
このアメリカからの縛りがずっと続いてきたのだ。
それがトランプ政権になってから状況が少し変わった。
2島の返還を前提にした交渉を認めたのだ。
それで、これまで交渉すらできなかったものが、
やっと交渉に進めることができたというのが真実だ。
それで前回の日露首脳会談後に、プーチン大統領も、
交渉を推し進めることに合意し、約束するとまで言った。
これまで70年近く交渉すらできなかったものが、
やっと交渉のスタートを切ることができたのだ。
ただし、これまでの70年で解決しなかった問題が、
そう簡単に解決するとは思えない。
まだまだ課題は多いと思うが、一歩前進できたことは間違いない。
相変わらず日本の新聞やテレビが、正しい報道が全くできていないことに憤りを感じる。
4月1日に発表される新元号が気になるところだ。
その4月には統一地方選が控えている。
鶴岡市では県議選候補者が一人増の少数激戦になりそうだ。
5月から新しい時代がスタートし、なんと今年のGWは
10連休だという。
そして6月にはG20が日本で開催され、
7月には参議院選挙がある。
場合によっては衆参ダブル選挙になる可能性も少なくない。
国会では予算審議の最中であるが、
野党は相変わらずのスタンスで揚げ足取りに躍起になっている。

【消費税増税について】
安倍首相は方針演説の中で、不退転の決意で実行すると言っている。
しかし、それは官僚が準備した原稿をそのまま読み上げただけで、
以前からリーマンショック級の事態が生じたら見直すとも言っている。
予算が通るまでは間違っても見直すとは言えないだろう。
言った時点で予算審議がストップし、内閣の総辞職になってしまう。
だが、予算成立後はわからない。
3月29日が期限のイギリスのEU離脱が混迷して、
こんな異常な事態が起こりうるのかというくらいに混沌としている。
このまま行ってしまったら、世界経済にとっては、リーマンショック級の大きな打撃となることは間違いない。
もうひとつ、中国の経済状況もかなり悪化している。
これも大きな危険を孕んでいる。
リーマンショック級の事件が2つも迫っているのだ。
しかも中国では消費税を16%から10%に引き下げる予定だという。
中国で下げると言っているときに、日本で増税するのは如何なものか。
こういった状況をみれば、消費増税を見送るのではないかと憶測できる。
【北方領土について】
もうひとつニュースで大きく取り上げているのが北方領土問題だ。
日本ではこの問題に関して、正確な歴史教育をしてこなかった。
政府にも大きな責任があると言える。
そもそも四島一括返還はあり得ない。
終戦の日付が日本と世界常識では違っている。
日本では8月15日を終戦記念日としているが、
世界の歴史では9月2日と認識されている。
終戦の後に違法に占拠されたという認識に無理がある。
日ソ共同宣言の後の経緯についても正しく伝えられていない。
1956年の日ソ首脳会談で、まず国交回復を先行させ、
平和条約締結後にソ連が歯舞群島と色丹島を日本に譲渡するという前提で、
改めて平和条約の交渉を実施するという合意がなされた。
ところが日本とソ連が仲良くなることを恐れたアメリカから待ったがかかった。
2島のみの返還は認めない。
4島一括返還でなければ沖縄の返還はあり得ないと恫喝された。
このアメリカからの縛りがずっと続いてきたのだ。
それがトランプ政権になってから状況が少し変わった。
2島の返還を前提にした交渉を認めたのだ。
それで、これまで交渉すらできなかったものが、
やっと交渉に進めることができたというのが真実だ。
それで前回の日露首脳会談後に、プーチン大統領も、
交渉を推し進めることに合意し、約束するとまで言った。
これまで70年近く交渉すらできなかったものが、
やっと交渉のスタートを切ることができたのだ。
ただし、これまでの70年で解決しなかった問題が、
そう簡単に解決するとは思えない。
まだまだ課題は多いと思うが、一歩前進できたことは間違いない。
相変わらず日本の新聞やテレビが、正しい報道が全くできていないことに憤りを感じる。
Posted by 五十嵐かずひこ at
11:33
│Comments(0)