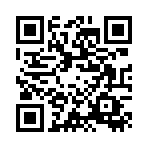2019年02月15日
平成の経済史
平成の時代がもうすぐ終わろうとしている。
バブル経済で始まった平成の時代。
そしてバブル崩壊後デフレに突入した失われた20年。
やっと少し出口が見えてきたアベノミクス。
この時代を、大蔵官僚として20年、
その後、学者として10年、平成の世を過ごしてきた高橋洋一教授の著書、
「平成経済史」を読み解きながら紹介していきたいと思う。

【固定相場制への誤解が生んだ「プラザ合意」のデタラメ解釈】
昭和60(1985)年、ニューヨークのプラザ・ホテルで行われたG5において、
いき過ぎたドル高を是正する「プラザ合意」が発表された。
一般的にはドル高是正のために各国が外為市場に協調介入することになったとされているが、
真相は違う。
実は為替に介入するある状況をカッコつけて言い換えただけなのだ。
プラザ合意以降、「アメリカの圧力によって、政府が円高誘導をするようになた」といわれているが、
これはまったくのウソ。
むしろ「政府が為替に介入しなくなったことで円高になった」というのが正しい。
単に「介入をやめます」と宣言しただけのことを、
「プラザ合意」とカッコつけて言い換えているのが実情なのだ。
戦後長らく続いた1ドル=360円という円ドル相場。
なぜこれが続いたかについて、多くの人が
「固定制だからレートが変わらなかった」と思っているだろう。
だが、それは戦後日本経済における
”大いなる誤解”なのだ。
実は為替が絶対に動かないように、
政府は裏でガンガン介入してレートを維持していた。
つまり固定相場制というのは、
政府が為替に介入しまくることで初めて維持できるものなのである。
このことを前提にして、固定相場制から変動相場制に移行したとされる昭和48年以降を考えてみよう。
このときも、「変動相場制になりました。あとは市場に任せます」
というのは建前であって、実際には「ダーティ・フロート」と呼ばれる為替介入がずっと続けられていた。
ありていに言えば、円を安く設定しておくために、
裏では猛烈にカネを擦りまくっていた訳である。
ところがプラザ合意以降は、そうした介入をすることはなくなった。
為替レートを市場に任せ、本当の意味での変動相場制にしたのだ。
介入がなくなると、為替の動きはきわめてシンプルになる。
金融緩和で円の量を増やせば、円の価値がドルに対して相対的に低くなるから円安になる。
逆に、各国が金融緩和を進めているのに円の量を増やさなければ、円の価値が上がって円高に振れる。
実際に、プラザ合意前の円ドルレートは1ドル=235円前後だったが、
1年後には150円前後になった。
ところが円高不況の心配もなんおその。
プラザ合意からときを経ずして、
日本は「バブル景気」に突入していく。
※高橋洋一著「平成経済史」より転載。
バブル経済で始まった平成の時代。
そしてバブル崩壊後デフレに突入した失われた20年。
やっと少し出口が見えてきたアベノミクス。
この時代を、大蔵官僚として20年、
その後、学者として10年、平成の世を過ごしてきた高橋洋一教授の著書、
「平成経済史」を読み解きながら紹介していきたいと思う。

【固定相場制への誤解が生んだ「プラザ合意」のデタラメ解釈】
昭和60(1985)年、ニューヨークのプラザ・ホテルで行われたG5において、
いき過ぎたドル高を是正する「プラザ合意」が発表された。
一般的にはドル高是正のために各国が外為市場に協調介入することになったとされているが、
真相は違う。
実は為替に介入するある状況をカッコつけて言い換えただけなのだ。
プラザ合意以降、「アメリカの圧力によって、政府が円高誘導をするようになた」といわれているが、
これはまったくのウソ。
むしろ「政府が為替に介入しなくなったことで円高になった」というのが正しい。
単に「介入をやめます」と宣言しただけのことを、
「プラザ合意」とカッコつけて言い換えているのが実情なのだ。
戦後長らく続いた1ドル=360円という円ドル相場。
なぜこれが続いたかについて、多くの人が
「固定制だからレートが変わらなかった」と思っているだろう。
だが、それは戦後日本経済における
”大いなる誤解”なのだ。
実は為替が絶対に動かないように、
政府は裏でガンガン介入してレートを維持していた。
つまり固定相場制というのは、
政府が為替に介入しまくることで初めて維持できるものなのである。
このことを前提にして、固定相場制から変動相場制に移行したとされる昭和48年以降を考えてみよう。
このときも、「変動相場制になりました。あとは市場に任せます」
というのは建前であって、実際には「ダーティ・フロート」と呼ばれる為替介入がずっと続けられていた。
ありていに言えば、円を安く設定しておくために、
裏では猛烈にカネを擦りまくっていた訳である。
ところがプラザ合意以降は、そうした介入をすることはなくなった。
為替レートを市場に任せ、本当の意味での変動相場制にしたのだ。
介入がなくなると、為替の動きはきわめてシンプルになる。
金融緩和で円の量を増やせば、円の価値がドルに対して相対的に低くなるから円安になる。
逆に、各国が金融緩和を進めているのに円の量を増やさなければ、円の価値が上がって円高に振れる。
実際に、プラザ合意前の円ドルレートは1ドル=235円前後だったが、
1年後には150円前後になった。
ところが円高不況の心配もなんおその。
プラザ合意からときを経ずして、
日本は「バブル景気」に突入していく。
※高橋洋一著「平成経済史」より転載。
Posted by 五十嵐かずひこ at
22:01
│Comments(0)