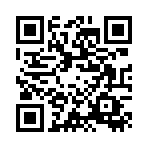2019年01月24日
自殺者減少の本当の理由
警察庁が18日発表した自殺統計によれば、2018年の全国の自殺者数は2017年より723人少ない2万598人(3.4%減)で、9年連続減少した。2.1万人を下回ったのは37年ぶり。人口10万人当たりの自殺者数(自殺死亡率)は0.5人減って16.3人。1978年統計開始以来、最少になった。
嘉悦大学教授の高橋洋一氏は自殺者の減少は金融緩和政策の「成果」だと解説している。
自殺と金融政策がなかなか結びつかないというのが、一般の人の感覚だろう。
だが米国などでは金融政策は雇用政策だと認識されているし、日本でも失業率が低くなると、自殺率が下がる傾向があるのだ。
自殺の原因・動機が複雑なことは確かだが、景気動向と密接にからむものもある。
警察庁では、自殺の原因・動機を、家庭問題、健康問題、経済生活問題、勤務問題、男女問題、学校問題、その他に分けている。
原因や動機の中で、健康問題と失業などの経済生活問題が占める割合は、年によって大きく変動し、その度合いは景気の動向に密接に関係がある。
具体的には、景気が悪く失業率が高くなると自殺率は上がり、逆に、好況で失業率が低くなると自殺率が下がる傾向がある(図1)。

高橋教授の推計では、1998年-2018年の両者の相関係数は0.86になっている。
失業率を1%低下させることができると、自殺者を3000人程度、減らすことができる計算だ。
なお、こうした時系列については、トレンドの影響を受けるために、見かけ上の相関係数が高くなるという意見もあるが、トレンドを除去しても、失業率と自殺率の間には高い相関が見られる。
金融政策と雇用の関係を図式で表せば、次のようになる。
金融政策→実質金利変化→GDPギャップ変化→雇用→物価変化
ここで、GDPギャップ変化→雇用は、実質国内総生産の成長率と失業率の変化に負の相関がみられるという経験則、オークン法則そのものだ。実質GDP成長率が上昇すると失業率は低下する。
雇用→物価変化は、賃金上昇率と失業率に負の相関があり、さらに失業率と物価上昇率は密接な関連があるとするフィリップス曲線を示す。
この図式の中で、金融政策→実質金利変化は、財政政策→有効需要変化と置き換えてもいい。
そしてさらに、金融緩和の結果、雇用が増加すると、社会安定につながる。
失業率が低下すれば自殺率が低下するのと同様に、失業率の低下は犯罪率の低下とも相関があるからだ。
つまり、職が得られれば、経済生活問題による自殺は減り、犯罪も減る。こうしたことは、過去のデータからも確認できる。つまり、金融緩和すれば、自殺率や犯罪率は減少する。
こうして金融政策は、雇用創出という経済効果のほか、その副産物として社会を安定させるという効用がある。このことはもっと知られてもいいことだ。
だが、そもそも日本では金融政策が雇用政策であるということすら認識されていない。
昨年10月に出された白川方明・前日本銀行総裁の著書『中央銀行』にも、金融政策と雇用との関係の記述は一切ない。
また金融政策と社会安定の関係についての日銀の認識も、はっきり言えば心もとない。
金融政策と雇用でいえば、日本の経済学者で、上記のマクロ経済の関係を数量的に理解している学者は一流でも少ないように思われる。数学や統計の基礎訓練が海外と比較してできていないからだろう。
インフレ目標と雇用の関係についても、やや誤解がある。
インフレ目標は、雇用の増加に伴い一般的にはインフレ率が上がる傾向があるために、過度な雇用を作ろうとしてインフレ率が上がりすぎるのを防ぐ役割がある。
金融緩和によって失業率が低下する中、インフレ率が上がらないのは、デフレでない限り金融政策としてはそれほど失敗ということではない。
ただいずれにしても、アベノミクスの金融緩和によって雇用が創出され失業率が低下した。その結果、自殺率が下がるのは予想通りだ。
それが、冒頭の警察庁データでも確認できたわけだ。
金融政策と雇用、失業率と自殺率の相関について、ここまでは全国レベルのマクロの話を書いたが、地方レベルでも同様の傾向になることが多い。
ただし、全国レベルの自殺率は、基本的に景気や失業率、もっと言えば金融政策と相関があるといっていいが、地方の自治体レベルでは、自治体独自の取り組みによって、自殺率が全国を下回ったりする(逆に工夫努力がされないと上回る)ことがある。
一例として大阪府を取り上げよう。
図2を見れば大阪府の自殺率(10万人当たり自殺者数)も、2008年頃から、全国と同様に低下している。

そこで、全国の数字をベンチマークとして、大阪の自殺率-全国の自殺率を見てみると、次のようになる。
2000年-2007年の平均は▲1.4人、2008年-2017年平均は▲2.7人だ。
大都市は所得水準が高いことから、自殺率は全国平均より低い。大阪府の場合も、2008年に橋下府政になる以前も全国平均より低かったが、橋下府政以降、差は広がっている。
これは、橋下府政以降、行政が雇用創出や自殺防止などに取り組んだからだと、考えている。
******************************************
※以上、ダイヤモンドオンライン:「高橋洋一の俗論を撃つ」より引用
嘉悦大学教授の高橋洋一氏は自殺者の減少は金融緩和政策の「成果」だと解説している。
自殺と金融政策がなかなか結びつかないというのが、一般の人の感覚だろう。
だが米国などでは金融政策は雇用政策だと認識されているし、日本でも失業率が低くなると、自殺率が下がる傾向があるのだ。
自殺の原因・動機が複雑なことは確かだが、景気動向と密接にからむものもある。
警察庁では、自殺の原因・動機を、家庭問題、健康問題、経済生活問題、勤務問題、男女問題、学校問題、その他に分けている。
原因や動機の中で、健康問題と失業などの経済生活問題が占める割合は、年によって大きく変動し、その度合いは景気の動向に密接に関係がある。
具体的には、景気が悪く失業率が高くなると自殺率は上がり、逆に、好況で失業率が低くなると自殺率が下がる傾向がある(図1)。

高橋教授の推計では、1998年-2018年の両者の相関係数は0.86になっている。
失業率を1%低下させることができると、自殺者を3000人程度、減らすことができる計算だ。
なお、こうした時系列については、トレンドの影響を受けるために、見かけ上の相関係数が高くなるという意見もあるが、トレンドを除去しても、失業率と自殺率の間には高い相関が見られる。
金融政策と雇用の関係を図式で表せば、次のようになる。
金融政策→実質金利変化→GDPギャップ変化→雇用→物価変化
ここで、GDPギャップ変化→雇用は、実質国内総生産の成長率と失業率の変化に負の相関がみられるという経験則、オークン法則そのものだ。実質GDP成長率が上昇すると失業率は低下する。
雇用→物価変化は、賃金上昇率と失業率に負の相関があり、さらに失業率と物価上昇率は密接な関連があるとするフィリップス曲線を示す。
この図式の中で、金融政策→実質金利変化は、財政政策→有効需要変化と置き換えてもいい。
そしてさらに、金融緩和の結果、雇用が増加すると、社会安定につながる。
失業率が低下すれば自殺率が低下するのと同様に、失業率の低下は犯罪率の低下とも相関があるからだ。
つまり、職が得られれば、経済生活問題による自殺は減り、犯罪も減る。こうしたことは、過去のデータからも確認できる。つまり、金融緩和すれば、自殺率や犯罪率は減少する。
こうして金融政策は、雇用創出という経済効果のほか、その副産物として社会を安定させるという効用がある。このことはもっと知られてもいいことだ。
だが、そもそも日本では金融政策が雇用政策であるということすら認識されていない。
昨年10月に出された白川方明・前日本銀行総裁の著書『中央銀行』にも、金融政策と雇用との関係の記述は一切ない。
また金融政策と社会安定の関係についての日銀の認識も、はっきり言えば心もとない。
金融政策と雇用でいえば、日本の経済学者で、上記のマクロ経済の関係を数量的に理解している学者は一流でも少ないように思われる。数学や統計の基礎訓練が海外と比較してできていないからだろう。
インフレ目標と雇用の関係についても、やや誤解がある。
インフレ目標は、雇用の増加に伴い一般的にはインフレ率が上がる傾向があるために、過度な雇用を作ろうとしてインフレ率が上がりすぎるのを防ぐ役割がある。
金融緩和によって失業率が低下する中、インフレ率が上がらないのは、デフレでない限り金融政策としてはそれほど失敗ということではない。
ただいずれにしても、アベノミクスの金融緩和によって雇用が創出され失業率が低下した。その結果、自殺率が下がるのは予想通りだ。
それが、冒頭の警察庁データでも確認できたわけだ。
金融政策と雇用、失業率と自殺率の相関について、ここまでは全国レベルのマクロの話を書いたが、地方レベルでも同様の傾向になることが多い。
ただし、全国レベルの自殺率は、基本的に景気や失業率、もっと言えば金融政策と相関があるといっていいが、地方の自治体レベルでは、自治体独自の取り組みによって、自殺率が全国を下回ったりする(逆に工夫努力がされないと上回る)ことがある。
一例として大阪府を取り上げよう。
図2を見れば大阪府の自殺率(10万人当たり自殺者数)も、2008年頃から、全国と同様に低下している。

そこで、全国の数字をベンチマークとして、大阪の自殺率-全国の自殺率を見てみると、次のようになる。
2000年-2007年の平均は▲1.4人、2008年-2017年平均は▲2.7人だ。
大都市は所得水準が高いことから、自殺率は全国平均より低い。大阪府の場合も、2008年に橋下府政になる以前も全国平均より低かったが、橋下府政以降、差は広がっている。
これは、橋下府政以降、行政が雇用創出や自殺防止などに取り組んだからだと、考えている。
******************************************
※以上、ダイヤモンドオンライン:「高橋洋一の俗論を撃つ」より引用
Posted by 五十嵐かずひこ at 09:24│Comments(0)