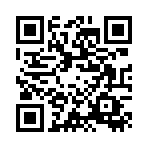2017年07月21日
なぜ財務省は「財政破綻する」と騒いでいるのか?
今読んでいる本、「国債の真実」の中で、
著者の高橋洋一氏が、なぜ財務省は増税したがるのか、
わかりやすく解説しているので、下記に紹介したい。
**************************
このままでは、いずれ日本は財政破綻する。
そして、日本国債は暴落する。
こういわれるようになって久しいが、
日本は一向に財政破綻しないし、
日本国債は一向に暴落しない。
その兆しを見せたことすらない。
財政破綻も国債暴落も、
「要因」がほとんどないのだから当たり前だが、
いまだにこう断じてはばからない人がいる。
自分たちの利益のために「あえて恐怖を煽っている人たち」もいるのだろう。
彼らは、データ的根拠や何をもって「暴落」とするのかを、
示していない場合が多い。
このことからも、単なるイメージ戦略であることがうかがわれる。
では、誰が、どのような利益のために、
財政破綻や国債暴落を主張しているのか。
一つは、財務省だ。
ただし、これは表では絶対いわない。
こっそりと裏でいうのである。
まず前提として、財務省は一貫して「増税派」と思っておいて間違いない。
その理由は、税金をたくさん集めて財政再建したいから、ではない。
じつは増税すると財務省の予算権限が増えて、
各省に対して恩が売れて、はては各省所管の法人への
役人の天下り先の確保につながるからだ。
驚いたかもしれないが、こうした思惑があるからこそ、
財務省は「いつだってスキあらば増税したい人たち」なのである。
なぜ増税が財務省の権限を増すことになるのか。
単純な話である。
まず、予算を実質的に膨らませることができる。
こういうと、経済成長によって「税収」が増えても同じという声もあるが、
それは素人論議だ。
経済成長があれば、要求官庁は経済成長に見合う経費増も要求する。
経済成長は財務省のおかげでないので、「税収」増の分だけ予算増となっても、
要求官庁は財務省に恩を感じない。
ところが、「増税」であれば、その増加分は財務省のおかげとなって、
財務省はその分の予算配分をするときに、各省庁に恩をきせられるのだ。
予算増の恩恵を受けた省庁は、その見返りに自分の所管する法人などに
財務省からの天下りを認めてやる。
もちろん、この天下りは予算配分してもらった見返りであり、
国民の血税が使われている。
もう一つは、増税するときには、必ずといっていいほど
「例外処置」が設けられる。
一緒くたに増税するのではなく、「こういうケースは税が軽減される」とか、
「今回の増税は、こういう業界は例外とする」といったように、
特定の業界や特定の層を優遇する処置がとられるのだ。
2014年の消費増税の際に、「軽減税率」が議論されていたことを覚えているだろうか。
「生活必需品は増税されない」とか「新聞は増税されない」などど、
いっとき、かまびすしかった。
これも要は例外処置に関する議論だったのだ。
ただし、どういう場合に例外処置が設けられるかは、
財務省のさじ加減だ。
もっともらしい理屈をつけて例外処置を設けるが、
そのじつ「この業界を特例とすることには、どんな利益があるのか」
という計算が働いていると見ていい。
これが、「あのとき優遇したのだから、引退した官僚の受け皿を提供しなさいよ」
という具合に、天下り先の確保につながるわけだ。
まったく呆れた利己思考だが、実際に大蔵省(現・財務省)に
身を置いたことがある私が自らの体験からいう話である。
**********************************

著者の高橋洋一氏が、なぜ財務省は増税したがるのか、
わかりやすく解説しているので、下記に紹介したい。
**************************
このままでは、いずれ日本は財政破綻する。
そして、日本国債は暴落する。
こういわれるようになって久しいが、
日本は一向に財政破綻しないし、
日本国債は一向に暴落しない。
その兆しを見せたことすらない。
財政破綻も国債暴落も、
「要因」がほとんどないのだから当たり前だが、
いまだにこう断じてはばからない人がいる。
自分たちの利益のために「あえて恐怖を煽っている人たち」もいるのだろう。
彼らは、データ的根拠や何をもって「暴落」とするのかを、
示していない場合が多い。
このことからも、単なるイメージ戦略であることがうかがわれる。
では、誰が、どのような利益のために、
財政破綻や国債暴落を主張しているのか。
一つは、財務省だ。
ただし、これは表では絶対いわない。
こっそりと裏でいうのである。
まず前提として、財務省は一貫して「増税派」と思っておいて間違いない。
その理由は、税金をたくさん集めて財政再建したいから、ではない。
じつは増税すると財務省の予算権限が増えて、
各省に対して恩が売れて、はては各省所管の法人への
役人の天下り先の確保につながるからだ。
驚いたかもしれないが、こうした思惑があるからこそ、
財務省は「いつだってスキあらば増税したい人たち」なのである。
なぜ増税が財務省の権限を増すことになるのか。
単純な話である。
まず、予算を実質的に膨らませることができる。
こういうと、経済成長によって「税収」が増えても同じという声もあるが、
それは素人論議だ。
経済成長があれば、要求官庁は経済成長に見合う経費増も要求する。
経済成長は財務省のおかげでないので、「税収」増の分だけ予算増となっても、
要求官庁は財務省に恩を感じない。
ところが、「増税」であれば、その増加分は財務省のおかげとなって、
財務省はその分の予算配分をするときに、各省庁に恩をきせられるのだ。
予算増の恩恵を受けた省庁は、その見返りに自分の所管する法人などに
財務省からの天下りを認めてやる。
もちろん、この天下りは予算配分してもらった見返りであり、
国民の血税が使われている。
もう一つは、増税するときには、必ずといっていいほど
「例外処置」が設けられる。
一緒くたに増税するのではなく、「こういうケースは税が軽減される」とか、
「今回の増税は、こういう業界は例外とする」といったように、
特定の業界や特定の層を優遇する処置がとられるのだ。
2014年の消費増税の際に、「軽減税率」が議論されていたことを覚えているだろうか。
「生活必需品は増税されない」とか「新聞は増税されない」などど、
いっとき、かまびすしかった。
これも要は例外処置に関する議論だったのだ。
ただし、どういう場合に例外処置が設けられるかは、
財務省のさじ加減だ。
もっともらしい理屈をつけて例外処置を設けるが、
そのじつ「この業界を特例とすることには、どんな利益があるのか」
という計算が働いていると見ていい。
これが、「あのとき優遇したのだから、引退した官僚の受け皿を提供しなさいよ」
という具合に、天下り先の確保につながるわけだ。
まったく呆れた利己思考だが、実際に大蔵省(現・財務省)に
身を置いたことがある私が自らの体験からいう話である。
**********************************

Posted by 五十嵐かずひこ at 23:56│Comments(0)