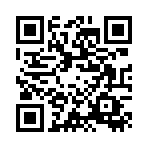2017年03月17日
ねんきん定期便
天気も回復して青空が見えてきましたが、
まだ寒い朝です。
早田地区の早田うり保存会のみなさんが、畑の整備作業をやってました。
早朝からご苦労様です。

さて今日、日本年金機構からねんきん定期便が届いた。
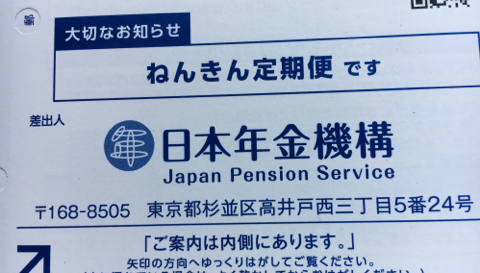
自分がいつからどのくらい年金を受け取ることができるのか、
この定期便を見るとわかるのでありがたい。
いい仕組みだと思う。
が、あと数年で私も年金を受給する歳になってしまったのかと
自分の年齢に驚いてしまう。
ところで、日本の年金制度について、
将来は破綻するのではないかと心配している方がけっこう多いように感じる。
それは、年金への不安をあおるメディアや政治家が多いからだと思う。
これだけ「危ない、危ない」と連呼されれば、心配になるのも無理はない。
では、ほんとうに日本の年金制度は危ないのか?
以下に下越大学教授で経済学者・数量分析家でもある
高橋洋一教授のコラム(zakzak by夕刊フジ)「日本の解き方」
からの記事を転載させていただく。
これが真実だと私は思います。
***************************************************
年金について国会審議がなされると、野党はすぐに「年金カット法案」
などとレッテル貼りをして猛反対し、メディアも盛んに「年金が危ない」
「破綻する」などと騒ぎ立てる。
では、年金は本当に危ないのか。
筆者の答えは「きちんと制度運用していれば大丈夫」である。
もちろんメチャクチャな制度改悪や経済政策運営をすれば別だが、
現状の制度をきちんと運用すれば「破綻する」などと
大げさに悲観する必要はない。
にもかかわらず、なぜ日本では「年金が危ない」という議論ばかりが百出するのか。
それは、「年金が危ない」ということを強調することで得になる人がいるからだ。
財務省や厚生労働省は、もちろん表立ってそうは言っていない。
だが、「年金が危ない」という主張が世間でまかり通っていたほうが得な面がある。
財務省は消費税の増税を目指しているが、
実現するためには社会保障への不安が高まっているのに越したことはない。
一方、厚労省にとって年金は、「利権」や「天下り」の源泉になっているといえる。
もし、必要以上に「安心」を唱えてしまったら、そのうまみを削られかねない。
実は、金融機関も「年金が危ない」という常識が世の中で通用していた方が
仕事がしやすくなる。たしかに、公的な年金はあくまで「基礎的」な部分であって、
老後への備えはそれぞれに進めておく必要があるが、「公的年金が危ない」
と多くの人が思ってくれていたら、投資や年金保険といったさまざまな金融商品を
売りやすくなる。
そうなると、金融機関系のエコノミストたちもまた、
その利害から完全に自由になることは難しい。
こういう状況なので、きちんとした知識を持っていないと、
メディアの情報などに惑わされて、不安ばかり強くなってしまう。
年金について正しい知識を身につけなければ、結果として大きな損すらしかねない。
年金制度が入り組んで複雑化していることは事実だが、
本来は、きわめてシンプルな仕組みである。筆者が年金制度の理解のために
必要なポイントは次の3つであると思う。
第1に年金は「保険」であること。第2に「40年間払った保険料」と
「20年間で受け取る年金」の額がほぼ同じであること。
第3に「ねんきん定期便」は国からのレシートということだ。
この3つを理解することで、年金問題で信じられていることと実態が異なることや、
年金のあり方についてどう考えればよいかまで、驚くほど簡単にわかる。
*********************************************************
まだ寒い朝です。
早田地区の早田うり保存会のみなさんが、畑の整備作業をやってました。
早朝からご苦労様です。

さて今日、日本年金機構からねんきん定期便が届いた。
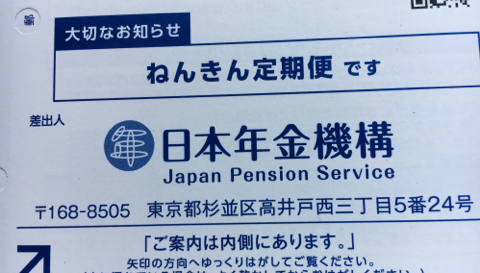
自分がいつからどのくらい年金を受け取ることができるのか、
この定期便を見るとわかるのでありがたい。
いい仕組みだと思う。
が、あと数年で私も年金を受給する歳になってしまったのかと
自分の年齢に驚いてしまう。
ところで、日本の年金制度について、
将来は破綻するのではないかと心配している方がけっこう多いように感じる。
それは、年金への不安をあおるメディアや政治家が多いからだと思う。
これだけ「危ない、危ない」と連呼されれば、心配になるのも無理はない。
では、ほんとうに日本の年金制度は危ないのか?
以下に下越大学教授で経済学者・数量分析家でもある
高橋洋一教授のコラム(zakzak by夕刊フジ)「日本の解き方」
からの記事を転載させていただく。
これが真実だと私は思います。
***************************************************
年金について国会審議がなされると、野党はすぐに「年金カット法案」
などとレッテル貼りをして猛反対し、メディアも盛んに「年金が危ない」
「破綻する」などと騒ぎ立てる。
では、年金は本当に危ないのか。
筆者の答えは「きちんと制度運用していれば大丈夫」である。
もちろんメチャクチャな制度改悪や経済政策運営をすれば別だが、
現状の制度をきちんと運用すれば「破綻する」などと
大げさに悲観する必要はない。
にもかかわらず、なぜ日本では「年金が危ない」という議論ばかりが百出するのか。
それは、「年金が危ない」ということを強調することで得になる人がいるからだ。
財務省や厚生労働省は、もちろん表立ってそうは言っていない。
だが、「年金が危ない」という主張が世間でまかり通っていたほうが得な面がある。
財務省は消費税の増税を目指しているが、
実現するためには社会保障への不安が高まっているのに越したことはない。
一方、厚労省にとって年金は、「利権」や「天下り」の源泉になっているといえる。
もし、必要以上に「安心」を唱えてしまったら、そのうまみを削られかねない。
実は、金融機関も「年金が危ない」という常識が世の中で通用していた方が
仕事がしやすくなる。たしかに、公的な年金はあくまで「基礎的」な部分であって、
老後への備えはそれぞれに進めておく必要があるが、「公的年金が危ない」
と多くの人が思ってくれていたら、投資や年金保険といったさまざまな金融商品を
売りやすくなる。
そうなると、金融機関系のエコノミストたちもまた、
その利害から完全に自由になることは難しい。
こういう状況なので、きちんとした知識を持っていないと、
メディアの情報などに惑わされて、不安ばかり強くなってしまう。
年金について正しい知識を身につけなければ、結果として大きな損すらしかねない。
年金制度が入り組んで複雑化していることは事実だが、
本来は、きわめてシンプルな仕組みである。筆者が年金制度の理解のために
必要なポイントは次の3つであると思う。
第1に年金は「保険」であること。第2に「40年間払った保険料」と
「20年間で受け取る年金」の額がほぼ同じであること。
第3に「ねんきん定期便」は国からのレシートということだ。
この3つを理解することで、年金問題で信じられていることと実態が異なることや、
年金のあり方についてどう考えればよいかまで、驚くほど簡単にわかる。
*********************************************************
Posted by 五十嵐かずひこ at 10:24│Comments(0)